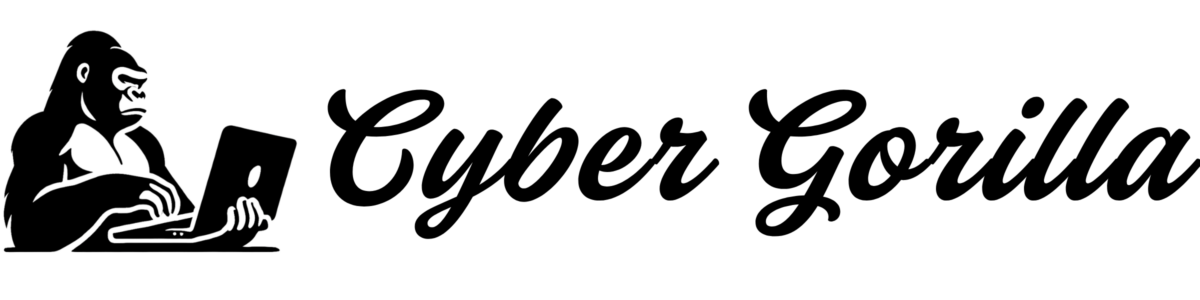ホスティングとハウジングの違いがよくわからず、自社にはどちらが合っているのか、運用やコスト・セキュリティまで考慮して最適な選択をどうすれば良いのか悩んでいます。



こうした疑問に答えます。
- ホスティングとハウジングの違いと選び方
- 各サービスのメリット・デメリット比較
- クラウドを含めた最新サーバー運用の選択肢
ホスティングとハウジングは、サーバーを用意・運用する主体や管理範囲などに明確な違いがあります。目的や体制によって最適なサービスが変わるため、それぞれの特徴を理解することが重要です。
ホスティングハウジングの違いを知れば、事業にふさわしい選択肢が見えてきます。さらに、オンプレミスとハウジングの違いについても解説しているので、まずは記事を最後までご覧ください。
ホスティングとハウジングの基本的な違いを徹底比較


サーバーを準備する際には、ホスティングとハウジングのどちらを選ぶかで運用負担やコスト、管理範囲が大きく変わります。ここではホスティングとハウジングの違いを詳しく解説します。
ホスティングとは?サーバー管理をお任せできるサービス
ホスティングとは、サーバー機器も含めて外部事業者からサーバーそのものを借りるサービス。一般的には「レンタルサーバー」とも呼ばれ、契約した分のディスク容量やスペック内でWebサイトの運営やメールシステムなどを使うことができます。
特徴として、サーバー自体の所有権や運用保守管理はすべて事業者側にあります。利用者はアプリケーションの設定やホームページの更新に集中可能。
物理的な設備や電源トラブルなどの対応もホスティング側が担うため、サーバー運用の知識が少なくても始めやすい点が最大のメリットです。特に初期投資が抑えられるので、小規模事業やスタートアップユーザーにも人気があります。
ハウジングとは?自社のサーバーを預けるサービス
ハウジングは、自社が所有するサーバー機器を専門のデータセンターに設置し、そこのインフラを借りるサービス。ラックスペース・電源・回線などをデータセンターから提供されます。
つまり、サーバー本体の調達や構築は自社で行います。安全性やネットワーク・電源の強靭さなどはデータセンター側のプロ仕様を利用。
サーバーの運用・管理は原則として自社で責任を持つ必要があり、自由度は高いものの、専門的な知識や人的リソースが求められます。ハード故障時の対応やOSのアップデートなども自社で実施することになります。
責任範囲やコスト構造で見る両者の明確な違い
ホスティングとハウジングの違いをまとめると、以下のようになります。
| 項目 | ホスティング | ハウジング |
|---|---|---|
| サーバー機器 | サービス提供者が所有・管理 | ユーザー(自社)が所有・管理 |
| 初期コスト | 低い(サーバー購入不要、月額利用が多い) | 高い(サーバー機器購入・運搬費が必要) |
| 運用負担 | サービス事業者へ委託可能 | 自社運用(障害対応・保守も自社) |
| カスタマイズ | 制限あり(提供プラン内のみ対応) | 自由度が高い(全て自社仕様に設定可能) |
| セキュリティ | 標準サービスに依存(独自設定に制限あり) | 高度な制御が可能(自社ポリシーに合わせた設定ができる) |
| 主な対象 | ITリソースが限定的な企業、個人、中小事業 | 特殊要件や高負荷サイト、大規模・官公庁・金融機関 |
- ホスティングは「手軽さ」と「低コスト」が魅力ですが、自由度や特殊な要求への対応には限界があります
- ハウジングは「機密性」や「高度なカスタマイズ」を重視しつつ、コストや運用リソース面の負担が大きくなります
選択時のポイントとしては以下が重要。
- どの程度システム全体をコントロールしたいか
- 初期投資やランニングコストをどこまで許容できるか
- 社内にサーバー運用のスキルや人材がどれだけいるか
近年ではホスティングハウジング以外にも、クラウドサービスが急速に拡大。両者の”いいとこ取り”ができる選択肢も増えています。インフラの運用負担と可用性・拡張性のバランスを考慮しながら、自社に最適なサービスを選定することが重要です。


ホスティングを利用するメリット


ホスティングとハウジングを比較検討する際、ホスティングは多くの企業や個人が選ぶ人気のサーバー運用方法です。ホスティングサービスの最大の特徴は、サーバー本体を所有せず、必要な容量やスペックのサーバーを外部の事業者から借りて利用できる点。これにより、専門知識がなくても安心してオンラインサービスを始められます。
初期費用を抑えて短期間で導入できる
ホスティングとハウジングの違いの中でも、最も大きなポイントが初期費用の違い。ホスティングはサーバーを購入する必要がなく、レンタルという形でサービスを利用できるため、導入時の初期費用を大幅に抑えられます。
サーバー機器の購入や設置、インフラ整備などの負担も不要です。レンタルサーバーを契約すれば、申込みから数時間~数日で環境が整い、すぐにWebサイトの公開やメールサービスの利用が始められます。
サーバーの運用や保守の負担を軽減できる
ハウジングとホスティングの違いで重要な点が、運用負担の違い。ホスティングでは、サーバーの運用・保守などの専門的な業務をサービス提供会社に任せられます。
サーバーの監視、障害対応、定期的なメンテナンスやセキュリティ対策もホスティング事業者が実施。利用者は本来の業務やサービス運営に専念でき、自社のIT人材のリソースも最小限で済みます。
専門的な知識がなくても利用しやすい
オンプレミスやハウジングと比較して、ホスティングは専門知識がなくても利用を開始できる点が魅力。契約手続きや初期設定、メールやドメイン設定も分かりやすくガイドされており、パネル操作だけで主要な機能をカスタマイズできます。
Webサイトやメールアカウントの作成・管理、データベースの利用なども直感的な管理画面から可能。そのため、IT専門部署を持たない中小企業やスタートアップにも適した選択肢となっています。


ハウジングを利用するメリット


ハウジングは自社で所有するサーバー機器を、外部のデータセンターに設置するサービス。自社オフィスにサーバーを置くのが難しい場合や、高いセキュリティ・安定したインフラ環境での運用を希望する場合に、ハウジングは大きなメリットを発揮します。
ホスティングとハウジングの違いを理解する上でも、ハウジングの特徴を把握することは重要。ここでは、そのメリットを3点に分けて詳しく解説します。
サーバー機器やOSを自由に選定できる高いカスタマイズ性
ハウジングの最大の魅力は、自社のニーズに合わせてサーバー機器やOS、ソフトウェア構成を自由に選択できる高いカスタマイズ性。ホスティングの場合は、サービス事業者側が用意したサーバーや構成を利用するため、自由度が限られます。
しかし、ハウジングは自社購入・所有のハードウェアを持ち込めるため、特殊なシステム要件や独自ソフトウェア、細かいネットワーク設定にも柔軟に対応可能。
- 独自のアプリケーションを動かしたい場合
- 社内で統一した特別なOS環境を構築したい場合
- オンプレミス環境と同等の自由度を求める場合
このような柔軟性は、業務要件が厳しい企業やシステムの拡張性・独自性を求める事業者にとって非常に大きなメリットとなります。
堅牢なファシリティで物理的なセキュリティを確保できる
ハウジングを活用することで、データセンターが提供する世界水準の物理的セキュリティ・ファシリティインフラを活用可能。データセンターには以下のような厳格な安全対策が施されています。
- 入退館管理システム
- 監視カメラによる24時間監視
- 耐震・防火設備
- 二重化された電源・空調設備
自社オフィスでは用意が難しい高度なセキュリティ体制のもと、大切なサーバー機器やデータを保護可能。また、ネットワーク回線や予備電源といったインフラ環境も最適化されているため、自然災害や停電など不測の事態にも高い可用性を確保できます。
既存のシステム資産をそのまま活用できる
自社で既にサーバー機器や各種ネットワーク機器を所有している場合、ハウジングを利用すれば既存資産をそのまま移設・活用可能。本格的なサーバーリプレースやシステム再構築の手間・コストを掛けず、運用場所だけを移す形で安定的なシステム継続ができます。
例えば、オンプレミス環境のサーバー運用からデータセンターへ移行するケースでは、システム設計やミドルウェアなど既存の体制を大きく変更する必要がありません。この特性は、予算を抑えたい企業や、既存資産を最大限活かしたい中長期的なIT戦略を考える企業にとって大きなメリット。
ホスティングとハウジングの違いを理解して、自社の状況に最適なサービスを選択することが重要です。
ホスティングとハウジングの選び方と注意点
ホスティングとハウジングは、サーバー運用における代表的な外部サービス。その選択は自社の技術力や事業計画に大きく影響します。
それぞれに異なる特徴とメリット・デメリットがあるため、正確な違いと判断基準を理解することが重要です。自社環境に最適なサービスを選択しましょう。
①:技術力と運用リソースで判断する
ホスティングとハウジングの大きな違いは「サーバーの所有と管理範囲」にあります。ホスティングはサービス事業者がサーバー本体を所有・運用管理し、利用者はその一部または全体を借りてサーバー運用を行う形式。
ハウジングは、自社で用意・所有したサーバー機器を外部データセンターへ設置します。インターネット回線や電源などのインフラのみを事業者から借りる仕組みです。
技術力や運用リソースが限定されている場合、ホスティングを選択することでサーバー運用管理の負担を大幅に軽減できます。一方、社内に十分なITスキルや運用ノウハウがあり、細かな設定や独自カスタマイズが必要なケースではハウジングのほうが柔軟に対応できるでしょう。
- ホスティングがおすすめな例
- IT担当者が少ない
- 運用管理の負担を減らしたい
- 一般的なWebサイトやメール利用が主目的
- ハウジングがおすすめな例
- 独自開発システムを使っている
- セキュリティ方針などカスタマイズが必須
- 自社でサーバー資産を保有・管理したい
②:求める自由度と将来の拡張性で判断する
選択肢の自由度や将来的な拡張性も両サービスで明確に異なります。ホスティングはサービス提供事業者が設けた仕様や利用規約に準拠する必要があるため、サーバーのOSやミドルウェア、ネットワーク設定などに一部制限がある点に注意。
ハウジングの場合は自社機器を自由に持ち込めるため構成変更や増設、システム移行なども柔軟に行えます。
オンプレミスハウジングホスティングとの比較でクラウド(IaaS)も近年重要になっています。クラウドは物理設備を持たずに必要なときに必要なだけリソースを増減できる点が特徴。急速な事業拡大や縮小にも素早く対応できるのが魅力です。
| サービス | 自由度・拡張性 | 適したケース |
|---|---|---|
| ホスティング | 一定の範囲で限定的 | 小〜中規模、拡張性より手軽さ重視 |
| ハウジング | 物理・論理とも高い自由度 | 大規模システム、独自要件にこだわりがある場合 |
| クラウド | 極めて高い(論理的拡張性) | 変動・拡大が見込まれる新規事業など |
特に将来的な事業成長やサービス追加を視野に入れる場合は、初期段階での選択肢の拡張性を重視すべき。必要に応じて最初はホスティング、規模拡大時にハウジングやクラウドに移行を検討するケースも増えています。
③:コスト構造の違いと事業規模で判断する
ホスティングとハウジングではコスト構造も大きく異なります。ホスティングは初期費用が抑えられ、毎月一定額を支払えば運用・保守までサービス提供者が対応してくれるため、総コストが予測しやすいのがメリット。
一方ハウジングはサーバー本体や関連機器の購入費用が初期に発生。さらに機器の保守管理やトラブル対応の人件費も必要です。
| サービス | 初期費用 | 月額費用 | 管理コスト | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|---|---|
| ホスティング | 低い | 比較的低価格 | 極小 | 管理負担が少ない | カスタマイズ性が低い |
| ハウジング | 高い(機器代等) | インフラ分のみ | 高い(自社負担) | 柔軟な設定・独自要件が実現できる | 管理負担と隠れコストに注意 |
| クラウド | ほぼ不要 | 利用量に比例 | 極小 | 必要な時だけ使えて拡張も容易 | 長期利用時は割高になる場合も |
事業規模によって選択肢も変わってきます。小規模事業や初期段階ではホスティングやクラウド。中〜大規模・専門要件が多い場合や他システムとの連携が必要な場合はハウジングが有効でしょう。
コストだけに目を奪われず、サポート体制・SLA・セキュリティ要件といった運用上の安心感や将来的な拡張性も合わせて検討することがトラブル回避のポイント。最新の傾向としては、サーバー運用と管理リスクを最小限にしたい企業が、クラウド(IaaS)を第一選択にするケースが増えています。


ホスティングとハウジング以外の選択肢 クラウド(IaaS)という可能性
ホスティングとハウジングは企業のサーバー運用方法として広く利用されています。近年ではクラウド(IaaS)という第三の選択肢も注目を集めています。
IaaSは従来の物理サーバー運用と比べて柔軟性や拡張性が高いのが特徴です。事業の成長や変化に対応しやすいという利点があります。
クラウド(IaaS)とは何か
クラウド(IaaS、Infrastructure as a Service)は、インターネット経由でサーバーやネットワークなどのインフラリソースを必要な分だけ借りて利用できるサービスです。ユーザーは物理サーバーを購入したり設置する必要がありません。
必要な時に必要なだけリソースを拡張・縮小できます。初期投資も最小限に抑えられます。
ハウジングとホスティングの違いと比較すると、それぞれの特徴が明確になります。ハウジングは「自分で用意したサーバー機器」を専門データセンターに設置し、インターネット回線や電源、セキュリティなど運用インフラを外部から借りる形です。
サーバー機器の運用・管理は利用企業の責任となります。ホスティングは「サービス事業者が用意したサーバー」をレンタルし、運用や保守も提供事業者に任せられるため、自社に高度な技術や専門知識がなくても利用しやすい点が特徴です。
なぜクラウドが主流になりつつあるのか
クラウドが急速に普及している理由は以下の点にあります。
- 初期投資を大幅に抑えられる
- システムの拡張・縮小が自由自在(スケーラビリティが高い)
- 高度なセキュリティ、バックアップや災害対策が標準で備わっていることが多い
- サーバーの運用管理を比較的シンプルにできる
特にスタートアップや新規事業、小規模部門などでは「今後の成長に合わせてITリソースを柔軟に増減したい」ニーズが強いです。この点でクラウドは非常に高い親和性を持つといえます。
近年はサーバーだけでなく、データベースやAI・機械学習など多彩なサービスがクラウド上で手軽に利用できるようになっています。従来のホスティングとハウジングの違いを超えて、さらに利便性が高まっています。
自社に最適なサービスを見つけるための最終チェックリスト
自社でどのサービスを選択すべきか検討する際は、単純なコスト比較だけでなく、以下の観点を網羅的にチェックすることが重要です。
- 自社でサーバー機器や運用環境を管理できる技術者がいるか
- 今後の事業拡大や変化に合わせて、どの程度スケーラビリティ(拡張性)が必要になるか
- セキュリティや監査要件(コンプライアンス)をどこまで重視するか
- 初期費用だけでなく、月額・保守費用や追加コストも含めてトータルで試算したか
- サポートや障害対応(SLA)が自社の要求水準と合致しているか
一般的な傾向として、以下の表のような比較ができます。オンプレミスハウジングホスティングそれぞれの特徴を理解して選択することが重要です。
| サービス | 初期費用 | 管理負担 | 拡張性 | セキュリティ | 利用におすすめのケース |
|---|---|---|---|---|---|
| ハウジング | 高い(自社で機器購入) | 重い(自社運用) | 物理的制約あり | 高(自社要件による) | 既存資産を最大限活用したい |
| ホスティング | 中程度~低い | 低い(事業者運用) | メニュー範囲内 | 標準的~高 | サーバー管理を外部委託したい |
| クラウド | 低い | 非常に低い | 非常に柔軟 | 標準的~非常に高 | 今後の拡張・縮小や新事業との親和性重視 |
自社のリソースと将来像をふまえ、総合的に判断することが最適な選択につながります。ホスティングハウジング違いを理解したうえで、自社に最適なサービスを見極めましょう。


まとめ:管理の手間と自由度で最適なサービスを選ぼう
ホスティングとハウジングには、サーバーの用意や運用責任、コスト構造、カスタマイズ性など本質的な違いがあります。自社のリソースや求める自由度によって最適な選択が変わります。
近年はクラウドサービスも加わり、管理負担や将来の拡張性まで考慮した総合的な判断が重要。本記事のポイントをおさらいします。
- ホスティングとは、事業者が用意するサーバーをレンタルして運用の手間を大幅に軽減できるサービス。初期費用や管理負担を抑えやすいのが特徴です。
- ハウジングは自社でサーバー機器を用意し、データセンターに設置・運用するため、カスタマイズ性や物理的なセキュリティが高まる一方、管理や運用の負担が伴います。
- どちらを選択するかは、技術力や運用リソース、将来の拡張性といった自社の状況とニーズをもとに総合的に判断することが大切。
ホスティングとハウジングの違いを明確に理解することで、サービス選定の不安や迷いが解消します。安心して自社に合う最適なサーバー環境を選択できるはず。
ぜひ、今日ご紹介したポイントやチェックリストを活用し、自社に最適な一歩を踏み出してください。


ホスティングとハウジングに関するよくある質問
- ハウジングとは何ですか?
-
ハウジングとは、自社が所有するサーバーをデータセンター内の専用ラックスペースに設置し、インターネット回線や電源などのインフラを借りるサービス。主に専門的な運用や高いセキュリティを求める企業向けです。
サーバーの運用・保守は基本的に利用者側が行います。そのため、サーバーの導入や管理に関する経験や技術力が必要。
- ホスティングとハウジングの違いは何ですか?
-
ホスティングは外部事業者が所有するサーバーをレンタルするサービス。サーバー本体の運用・管理は事業者が担当します。
一方ハウジングは、利用者が自前でサーバーを準備し、データセンターのインフラのみを借りて設置・管理する仕組み。つまり、ホスティングは運用負担が少なく初心者向き、ハウジングは自由度が高い分、高度な管理能力を要するということです。
- ホスティングとはどういう意味ですか?
-
ホスティングとは、ウェブサイトを公開したい企業や個人が、外部業者からサーバー自体をレンタルし、事業者に管理や保守を任せて利用できるサービス。利用者はサーバー購入や複雑なメンテナンス作業が不要です。
低コストかつ手軽に利用できるのが特徴。サーバー管理の専門知識がなくても利用しやすい点が多くの利用者に支持されています。